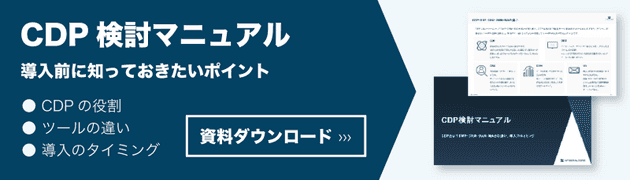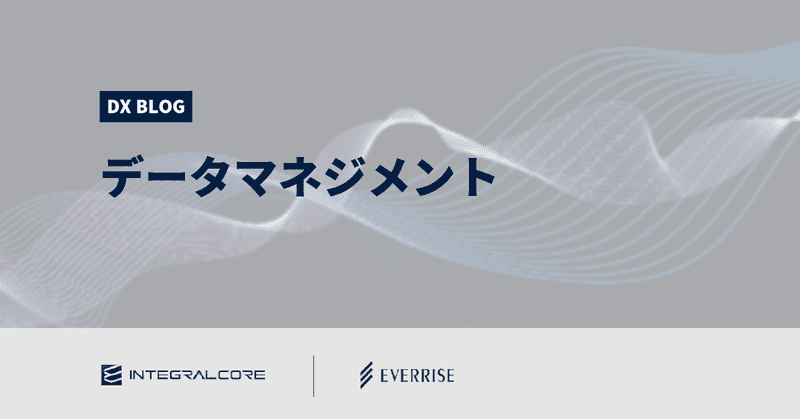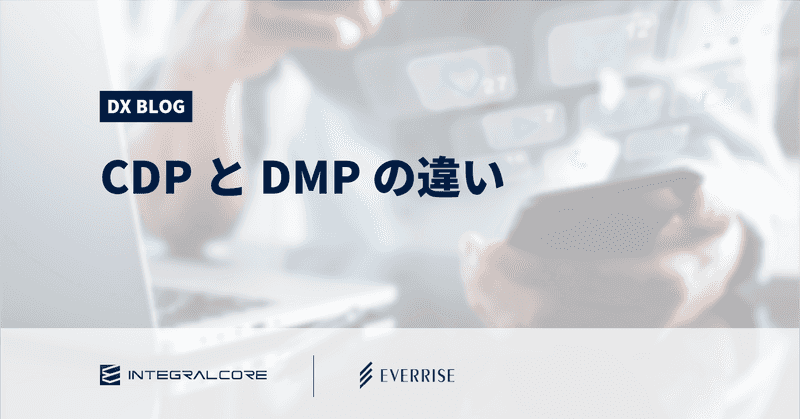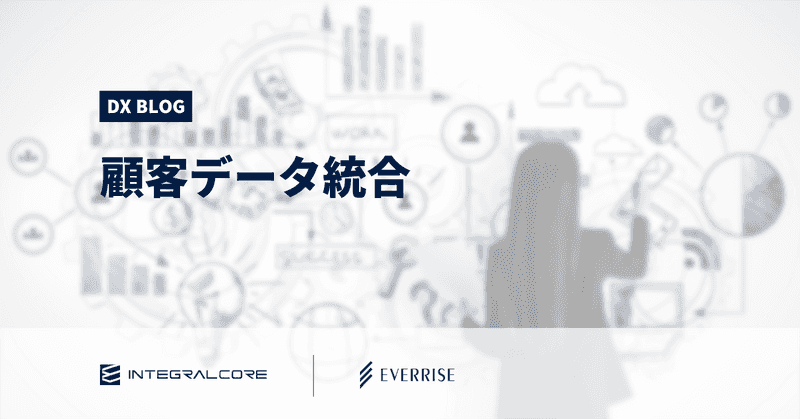企業によるデータ活用の取り組みが進む中で、顧客データを一元管理しマーケティングや業務改善に活用する基盤として、CDP(カスタマー データ プラットフォーム)を導入する動きが広がっています。
しかし、CDPには多様な製品があり、自社の目的や業務要件に合わないツールを選んでしまうと、期待どおりの成果は得られません。成果を最大化するには、自社に最適なCDPを選んだうえで、導入フローを把握して適切に進めることが重要です。
本記事では、CDP導入を考えるタイミングや導入手順とポイント、CDPの選び方について紹介します。
なお、CDPとほかのツールとの違いや部門別の活用例などについては、別記事で紹介しています。詳しくは下記の記事をご覧ください。
関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説
CDPの導入を考えるタイミング
CDP導入の検討タイミングは、顧客接点やマーケティング活動の複雑化・高度化の兆しが見え始めたときです。具体的には、下記のような課題が顕在化した場合が該当します。
こうした状況では、CDP導入が現実的な選択肢となります。
また、複数の事業部やツールがそれぞれ独立して顧客データを保持している状態を指す「データのサイロ化」が起きている場合、CDPを導入してデータ基盤を統合・共通化することで、部門間の連携強化やデータ活用の効率化が進み、結果としてコスト削減も期待できます。
関連:データのサイロ化とは?2つの原因と解決策、サイロ化を解消するツールを紹介
さらに、Cookie規制の強化やプライバシー保護の流れを受け、自社で一元管理できる1st Party Dataの整備が急務となっている場合も、CDP導入を検討すべきタイミングです。
CDPは単なるシステムではなく、顧客起点のマーケティングと全社的なデータ活用を支える基盤です。既存の仕組みに限界を感じ始めたときこそ、自社がCDPを必要とするフェーズにあるかを見直しましょう。
CDP導入の手順とポイント
CDPの導入は、単にデータを統合・可視化するための取り組みではありません。各事業部間やツールに分散していた顧客接点を再構築し、全社で活用できるデータ基盤を整備するプロジェクトです。
導入にあたっては「何のために導入するのか」「どの部門と連携して進めるのか」「どの段階で何を判断すべきか」といった視点を持ちながら、段階的かつ戦略的にプロジェクトを進める必要があります。
CDP導入を下記の4つのフェーズに分け、それぞれの目的・実施内容・関係者を整理しながら解説します。
- 準備フェーズ
- データ収集フェーズ
- 構築フェーズ
- 活用フェーズ
1.準備フェーズ
まずは、導入目的や活用目標(KPI)を明確にし、関係部門との合意形成を行います。営業・CS・情報システムなどの他部門と連携し、CDP活用に向けた共通認識を持つことが重要です。
主な作業と担当者は下記のとおりです。
| 作業内容 | 担当者 | |
|---|---|---|
| ビジネスの目的定義 | ・会社として目指す方向の明確化 ・顧客体験や業務効率などの優先課題の整理 |
・経営層 ・各事業部責任者 |
| 活用目標・KPIの設定 | ・売上・LTV・リテンション・コスト効率などの目標設定 | ・経営層 ・マーケティング部 |
| データ要件の整理 | ・既存データの棚卸し ・新たに取得・統合すべきデータの洗い出し ・対象ユースケースの仮説立案 |
・マーケティング部 ・情報システム部 ・各事業部担当者 |
CDP導入前には、統合対象となる各システムのデータ内容・担当者・外部ベンダーの有無などを把握し、社内のシステム・データ構造を整理しておくことが不可欠です。特に外部ベンダーが関与しているシステムでは、作業依頼から対応完了まで時間がかかることが多いため、早期に調整しておくことで後工程をスムーズに進めやすくなります。
なお、弊社EVERRISEでは、データ統合・活用に関する課題を抱えている企業さまを対象とした「データ統合アセスメントサービス」を提供しています。スムーズにデータを統合し、活用できる状態まで構築できるよう、データの整理や品質評価、プロジェクト計画の作成までサポートが可能です。
データ統合でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。データ統合アセスメントサービスについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。
無料資料:データ統合アセスメントサービスご紹介資料
2.データ収集フェーズ
CDPに取り込む顧客データの種類や収集方針を定め、安定的にデータを取得・統合できる仕組みを整備します。CDPでは個人情報を含むデータを扱うため、プライバシー保護や内部統制の観点から、ガバナンス設計や規約の整備も同時に進める必要があります。
主な作業と担当者は下記のとおりです。
| 作業内容 | 担当者 | |
|---|---|---|
| データの要件定義 | ・データ活用のユースケース策定 ・保有データの棚卸と整備 ・新たに取得が必要なデータの定義 ・データ間リレーションの把握 ・既存基盤との連携要否の整理 |
・マーケティング担当 ・情報システム部 ・各部門担当者 |
| データソースの信頼性評価 | ・対象データの鮮度・継続取得可否の確認 ・欠損・異常値の有無チェック ・定常取得の手段確保 |
・マーケティング担当 ・情報システム部 |
| データガバナンス設計 | ・アクセス権限の設計 ・監査ログ・変更履歴の取得方針設計 ・個人情報保護方針との整合 |
・マーケティング部 ・情報システム部 ・法務部 |
| プライバシーポリシー・利用規約の見直し | ・取得するデータの利用目的の明文化 ・社外向けポリシー・規約の改定準備 |
・マーケティング部 ・情報システム部 ・法務部 |
| データ取得設計 | ・データ取得方式の選定 ・I/F仕様、データ仕様の確認 ・DB・テーブル構造の設計 ・PIIの加工方式の定義 |
・マーケティング部 ・情報システム部 |
| データ取得実装・構築 | ・タグ・SDK・APIなどの実装 ・マッピングテーブル設計 ・ログ・マスタのテーブル構築 |
・マーケティング部 ・情報システム部 |
このフェーズでは、単に設計・実装を進めるだけでなく、継続的かつ安定的に運用できるか、という観点でデータ取得方法を選定することが重要です。
例えば、一時的にCSVファイルで取得可能なデータであっても、週次・月次といった定常運用が難しい場合は、CDPとしての実用価値は大きく損なわれます。また、システムの担当者や外部ベンダーとの調整を後回しにすると、構築後に再設計が必要になるリスクも高まります。
「技術的に作れるか」だけでなく「ビジネス要件や運用負荷を踏まえた持続可能な設計」を行うことで、導入後の運用効率を高め、想定した成果を引き出せるようになります。
関連:顧客データ収集の方法と有効なツール4選|収集すべき2種類のデータとは
3.構築フェーズ
データの収集が完了した後は、マーケティング施策や分析に活用できる状態へと加工・整形するフェーズに入ります。ETL・ELT処理を含むデータパイプラインの設計・構築を行い、データのクレンジングや名寄せ、セグメント定義の整備を通じて、ユーザーの行動や属性を正確に捉えられる環境を整備します。
また、BIツール・MAツール・広告配信ツールなどの活用先を見据えた中間テーブルや出力形式の設計、定常処理の自動化も、この段階で対応すべき重要項目です。
主な作業と担当者は下記のとおりです。
| 作業内容 | 担当者 | |
|---|---|---|
| データの加工・整形 | ・データパイプラインの設計・構築 ・データクレンジング・名寄せ処理 ・SQLなどによる加工・整形 ・セグメント作成 |
・情報システム部 |
| 中間テーブル設計 | ・集計用テーブルの設計 ・粒度や論理定義の合意形成 |
・マーケティング部当 ・情報システム部 ・各部門担当者 |
| データ連携設計(アウトプット設計) | ・BI・MA・広告ツールなどへの出力設計 ・データフォーマットや転送方式の標準化 |
・マーケティング部 ・情報システム部 |
| 処理自動化設計 | ・ETL実行スケジュールの設計 ・エラー検知・アラート再処理設計 |
・マーケティング部 ・情報システム部 |
注意すべきは、分析指標やセグメント条件の「定義の曖昧さ」を排除することです。定義が不明確なまま開発を進めると、施策やレポートにおいて誤った前提に基づく意思決定が行われるリスクがあります。
例えば、集計単位を「週」とする場合、開始日を日曜にするか月曜にするかで結果が異なります。また、データの定義としてwebトラッキングにおける訪問を集計する「セッション」でも、終了の定義を「最終ページからの経過時間」「特定行動の実行」「日をまたぐ場合」など、どの基準で設定するかによって解釈が異なります。こうした定義が統一されていなければ、同じ指標でも意味が変わってしまい、誤った分析や判断に繋がる恐れがあります。
こうした事態を防ぐには、マーケティング部・データ解析担当・情報システム部などの関係者全体で丁寧に合意形成を行うことが不可欠です。
4.活用フェーズ
このフェーズでは、CDPに蓄積されたデータを各種ツールと連携し、マーケティング施策や可視化に活用します。施策の設計から実行・効果測定・改善までのサイクルをスピーディーに回すことで、CDP導入の価値を最大化します。
主な作業と担当者は下記のとおりです。
| 作業内容 | 担当者 | |
|---|---|---|
| アウトプット連携 | ・広告配信プラットフォーム連携 ・自社システム連携(自社メディアレコメンド) ・各種外部ツール連携(CRM・MA・BIなど) |
・データ解析担当 ・マーケティング担当当 |
| 分析・可視化 | ・SQL・BIツールなどによる統合データ可視化 | ・データ解析担当 ・マーケティング担当 |
| 施策の設計 | ・顧客セグメントの定義 ・パーソナライズ施策の立案 ・オートメーションの設計 |
・マーケティング担当 |
| 施策の実行 | ・施策の配信実行 ・効果検証とPDCA運用の推進 |
・マーケティング担当 |
CDPは全社で活用可能なデータ基盤であり、その価値を最大限に発揮するためには、全社的にデータ活用文化を育成する必要があります。特に、BIツールによる可視化や自動配信ツールを扱う部門には、研修やオンボーディングを通じてスキル定着を促すことが効果的です。
また、CDPは一度導入すると簡単にリプレイスできるツールではないため、中長期的な運用を前提に、継続的に活用できる体制とガバナンスを構築することが不可欠です。「導入して終わり」ではなく「活用し続けるための仕組み」を計画的に整備することが、長期的な成果に繋がります。
CDPの選び方のポイント
CDP導入を検討する際「導入するとしたらどのツールが良いのか」と迷うケースは少なくありません。選定時の主な評価軸は、下記の4つです。
- 機能面
- 費用面
- 連携面
- 運用・サポート面
機能面
CDPに備わる機能が、自社の活用目的や業務要件に合致しているかを見極めることが重要です。下記のような要件に対応できるかを確認しましょう。
- リアルタイムでのセグメント更新が可能か
- ノーコードでのセグメント作成が業務レベルで運用可能か
- 施策別の効果測定やパフォーマンスの可視化が行えるか
また、BIツールとの連携・広告配信ツールへのエクスポート・スコアリング機能など、将来的な拡張を見据えて機能要件を整理することも重要です。
費用面
CDPは初期の導入費用だけでなく、ユースケースやデータ量に応じてランニングコストが発生します。主に下記の要素によって、総コストは大きく変わります。
- 月額(年額)利用料
- 外部ツールとの連携費用
- ユーザー数やデータ保管容量に対する費用
- APIコール数の上限と追加費用
- 技術的支援や追加開発の費用
オプション料金の有無やエンタープライズ契約が前提となるケース、技術支援の有償対応など、契約条件によって費用は大きく変動します。導入を比較する際は、必ず初期費用とランニングコストを含めたトータルコストで判断しましょう。
連携面
自社システムとの連携の容易さは、CDP選定における重要な判断基準です。一般的な連携対象には、下記のようなツールが含まれます。
- MAツール
- CRMツール
- BIツール
- 広告配信システム
- メール配信ツール
選定時には、自社で利用しているツールとの連携実績・API仕様の開示状況・バッチ処理の柔軟性を確認しましょう。LINE配信やレコメンド表示などリアルタイム性が求められる業務では、即時反映の可否や同期頻度も評価対象になります。
運用・サポート面
CDPは導入して終わりではなく、日々の運用・活用によって価値を生み出すツールです。下記の観点で、自社運用とベンダー支援の両面を確認します。
- レポート出力やKPIの可視化が現場レベルで可能か
- 定型作業を自動化できる設定機能があるか
- 初期設定・初期構築を伴走支援してくれるか
- 活用トレーニングや定例サポートを提供しているか
- 障害発生時の対応スキームと対応範囲が明確か
単なる機能提供だけでなく、中長期的な運用を見据えて継続的に支援できる体制を持つベンダーを選ぶことが、CDP活用の定着とビジネスの成果に繋がります。
自社に合ったCDPの選び方について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。よくある3つの失敗例とあわせて紹介しています。