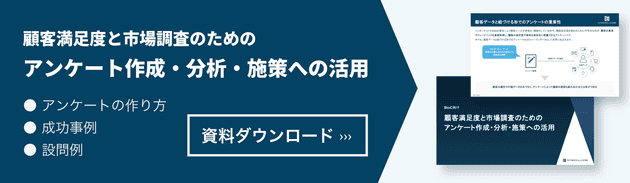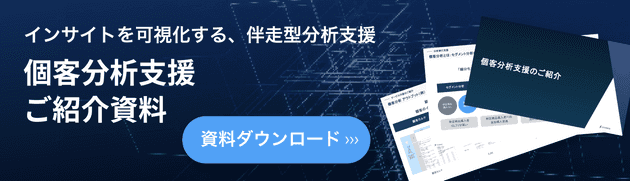顧客ニーズの多様化や市場環境の変化が進む中で「顧客理解」の重要性はあらためて高まっています。しかし実際には、表面的な分析や型通りの手法にとどまり、本質的な顧客理解に繋がっていないケースも少なくありません。
本記事では、顧客理解を深めるための具体的なアプローチを解説するとともに「なぜ顧客理解が進まないのか」といった課題の背景にも触れながら、効果的に顧客理解を進めるための5つのステップを紹介します。
顧客理解とは
顧客理解とは、顧客が求めている製品や商品を生み出したり、顧客にとって役に立つコミュニケーションを提供することで、売上の向上や顧客の継続的な利用を促進するために、自社の製品やサービスを利用している顧客の購買行動や属性などからニーズや考えを見出す取り組みのことです。
例えば、顧客が「どのような意図で商品を購入したのか」「購入を迷った他社製品はあったのか」「抱えていた不満・課題は何か」「自社サービスに対してどのような価値を感じたか」といった視点から情報を捉えることで、顧客の行動や選択の背景をより深く理解することができます。
従来の顧客理解の限界と本質的なアプローチ
「顧客理解」と言っても、その手法やアプローチは多岐にわたります。例えば、次のような取り組みが一般的に顧客理解の手段として広く用いられています。
- ペルソナやカスタマージャーニーマップを利用して顧客像を整理すること
- 顧客インタビューやユーザーヒアリングで生の声を集めること
- 行動・属性データをもとに分析し、顧客の傾向を捉えること
いずれもマーケティングや商品開発において有効なアプローチですが、実施すること自体が目的化してしまったり、想定した顧客像がいつの間にか実態とズレていたりするケースも少なくありません。
また、情報があふれる現在、顧客自身が「自分にとって必要・有益」と感じる情報だけを取捨選択するようになっており、企業からの一方的な情報発信だけでは、関心を持ってもらうことが難しくなっています。
こうした状況の中で、One to Oneマーケティングや顧客体験、CE(カスタマー・エンゲージメント)といった概念も広く語られていますが、それらを実現するには、顧客がどのような価値観・背景・動機を持っているのかを深く理解することが前提となります。
顧客の行動や価値観が多様化・複雑化する時代に、こうした形式的な「顧客理解」だけでは、顧客が求める体験と企業が届けたい価値との間にギャップが生まれ、結果として顧客に選ばれにくくなる恐れがあります。
顧客理解の主要なアプローチと課題
顧客理解の代表的なアプローチにはどのようなものがあるのか、それぞれの特徴と課題について紹介します。
ペルソナやカスタマージャーニーマップを用いた顧客理解
ペルソナは、理想的な顧客像を社内で共有するための有効な手法として、多くの企業で活用されています。また、カスタマージャーニーマップは、顧客が商品やサービスと接点を持つプロセスを可視化することで、接点ごとの課題や改善ポイントを明らかにするフレームワークであり、こちらも広く活用されています。
ただし、これらの手法が主観や思い込みに依存して設計されてしまうと、実際の顧客像との乖離が生じやすくなります。「こういった顧客がいるはず」と仮定して作られた図やストーリーは、現場の実態と噛み合わず、施策の方向性を誤らせる要因になりかねません。
関連:カスタマージャーニーとは?効果的なマップの作り方と2つの活用事例
インタビューやユーザーヒアリングでの顧客理解
インタビューやヒアリングは、顧客の声を直接聞くことで、言語化されていない課題や感情を探ることができる貴重なアプローチです。
一方で、得られた情報が一部の顧客に偏っていたり、インタビュアーの誘導によって本質が見えにくくなったりすることもあります。
また、定性情報は解釈の幅が広いため、誰が読んでも同じ示唆が得られるとは限らず、再現性や汎用性に課題を残すケースも見られます。
データ分析での顧客理解
性別・年齢・居住地などの属性情報は、多くの企業で顧客像を把握するための基本的なデータとして活用されています。これらにwebサイトの閲覧ログや購買履歴といった行動データを組み合わせることで、顧客像の全体像を大まかに描くことができます。
しかし、分析が属性情報や単純な購買データなどに偏ると「実際に何を重視して選んでいるのか」や「他と比べてなぜその商品を選んだのか」といった深層的な理解には繋がりにくくなります。属性ベースの分類だけでは、同じ年齢層でも価値観や購買行動が大きく異なる場合があり、施策設計の精度が落ちる可能性があります。
複雑化する顧客像の捉え方
本記事は、既存の手法を否定するものではありません。それぞれのアプローチには有効な場面があり、適切に活用すれば顧客理解を深める有力な手段となります。ただし、それぞれの手法には有効な場面がある一方で、カバーできる範囲には限界があり、単独では顧客の全体像を十分に描ききれない場合があります。
特に、セグメント分析やスコアリングなどの定量分析は、多くの企業で顧客理解の中核とされがちです。全体傾向の把握や施策効果の検証を効率的に行える一方で、数値から見えるのはあくまで「何が起きたのか」という結果です。そこから一歩踏み込み「なぜその行動が起きたのか」という背景や動機まで読み解くためには、定性的な視点や別のアプローチが欠かせません。
本記事では、こうした限界を踏まえつつ、顧客一人ひとりをより高い解像度で捉えるためのアプローチを紹介します。なお、今回は認知バイアスやタイプ分類などの心理学的アプローチには踏み込まず、マーケティングにおける顧客理解をテーマとして扱います。
顧客理解を深める2つの分析手法
顧客理解を深めるには、顧客の行動や意思決定の背景にある意識・感情の両面から情報を捉えることが重要です。ここでは、行動データと心理的なデータ、それぞれに着目した分析アプローチとその違いについて紹介します。
行動を対象とした分析
行動を対象とした分析とは、webサイトの閲覧履歴・メールの開封率・購買履歴など、実際の行動や成果に基づく数値データをもとに、顧客の傾向を把握するためのアプローチです。日々の接点で蓄積される行動データをもとに「何が起きているのか」を定量的に把握できます。
主な行動データの種類とその例は下記のとおりです。
| 行動データの種類 | データの例 |
|---|---|
| web行動データ |
・流入経路 ・訪問日時 ・閲覧ページ |
| アプリ内行動データ |
・アプリの起動日時 ・表示スクリーン(コンテンツ) ・イベント実行日時 |
| 購買データ |
・購入日時 ・商品名 ・売上金額 |
| 位置情報データ |
・来店・来場日時 ・特定行動の実行日時 |
こうした行動データをもとに、顧客全体の傾向やセグメントごとの特徴を把握するために、下記のような分析手法が用いられます。
- セグメンテーション分析
- 属性や行動パターンに応じて顧客を分類し、それぞれに最適なアプローチを検討
- 行動トレンド分析
- 購買や利用頻度などの変化を時系列で捉え、行動傾向や兆しを発見
- RFM分析
- 最新の購買日(Recency)、頻度(Frequency)、金額(Monetary)の3軸から優良顧客を抽出
- デシル分析
- 顧客を売上順に10等分し、上位層と下位層の構成や違いを分析
これらの分析を通じて、例えば「購入頻度は低いが1回あたりの単価が高い層」や「特定商品を購入した後に離脱しやすい層」などの特徴を捉えることができ、顧客全体の傾向やセグメントごとの特徴を把握可能です。
意識・感情を対象とした分析
意識・感情を対象とした分析とは、顧客の「なぜその行動をとったのか」「どのような価値を感じているのか」といった心理的な側面に着目し、行動の背景を深掘りするアプローチです。
例えば、同じ商品を購入したとしても「〇〇に惹かれたから買った」「以前使ってよかったからまた買った」「ほかに選択肢がなかったから仕方なく選んだ」など、意思決定に至る理由や期待値は人それぞれ異なります。
心理データには、下記のようなものがあります。
- 購入や利用の動機
- 商品・サービスに対する期待や不満の声
- ブランドや企業に対する印象
- 行動に至るまでの感情の変化や心理的ハードル
個別の意思決定プロセスや期待値に目を向けることで、見落とされがちな顧客の内面や背景に迫ることが可能になります。
こうしたデータは、主に下記のような手法によって収集・分析されます。
- ユーザーインタビュー(ヒアリング)
- 実際の顧客に対して一対一で深掘りする対話型調査
- アンケートの自由記述分析
- 数値化しにくい生の声から、傾向や共通点を抽出
- 行動観察(ユーザビリティテストなど)
- 顧客の操作や反応を観察し、言語化されない心理を推測
数値として把握できる行動データだけでは見えてこない「顧客の本音」や「行動の裏にある思考」を明らかにすることで、施策立案やサービス改善の精度を高めるうえで重要な視点を把握できます。
顧客アンケートの進め方や成功事例について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。そのままご利用いただけるアンケートの設問例についても紹介していますので、あわせてご活用ください。
無料資料:BtoC向け|顧客満足度と市場調査のためのアンケート作成・分析・施策への活用
行動と心理、両軸から捉える顧客理解
顧客理解を進めるうえで重要なのが、行動データと心理データを個別に分析するだけでなく、両者を掛け合わせて意思決定の背景にある価値観や感情を捉える視点です。
例えば、セグメント分析によって「細分化されたセグメントの傾向」を把握できますが、「なぜ継続してサービスを購入・利用しているのか」までは読み取れないことがあります。
顧客一人ひとりにフォーカスしてどのようにブランドを認知し、どのタイミングで好意を持ち、どの要因で離脱したのかといった一連のプロセスを、行動軸と心理軸の両面から捉えることで、売上やLTV向上に繋がる本質的なインサイトを導き出すことができます。
次章では「行動」と「心理」の両軸で顧客を深く掘り下げる、実践的なアプローチを具体的に紹介します。
顧客理解を進めるための5つのステップ
「行動」と「心理」の両軸で顧客を深く掘り下げ、顧客理解を進めるための5つのステップを紹介します。
- 目的・KPIを明確にする
- 必要なデータを収集・整理する
- 傾向把握のための分析を行う
- 顧客インサイトを掴むための分析を行う
- 分析結果をもとに施策を実行する
1.目的・KPIを明確にする
顧客理解の取り組みを始めるうえで、最初に明確にすべきなのが「なぜ顧客を理解したいのか」という目的の定義です。
顧客理解は、それ自体が目的化してしまうと「インタビューを実施すること」や「分析レポートを作ること」がゴールになりかねません。
しかし、本来の顧客理解は、マーケティングや商品改善、カスタマーサクセスなどの課題を解決するための手段であり、何を知りたいのか、なぜ知る必要があるのかを明らかにすることが出発点となります。
例えば、下記のような課題に対して「誰の・どのような情報を・どの行動や心理に対して得るべきか」を具体的に定義していきます。
- 「LTVが高い顧客の共通点を明らかにしたい」
- 「直近の解約理由を把握し、再発防止策を立てたい」
- 「商品の利用実態を掘り下げ、新しい価値提案に繋げたい」
また、目的に対してKPIが設定されていない場合は、まずその設定から着手する必要があります。KPIがなければ、どのデータを収集すべきか、どの分析手法を用いるべきかを判断できず、分析そのものを適切に進めることができません。
KPIを明確にすることで、必要なデータの特定から施策実行後の効果検証まで一貫性を持たせることが可能になり、改善サイクルも回しやすくなります。
関連:KGI・KPIとは?企業別の事例と設定手順、KPIツリーの作り方
2.必要なデータを収集・整理する
次に、設定した目的やKPIを検証するために、必要なデータを収集します。顧客理解の精度を高めるには、単にデータを集めるだけでなく、分析に使える形に整理しておくことが大切です。
はじめから大規模な仕組みを整える必要はなく、まずは必要なデータを集めてシンプルに整形・分析してみることから始めるのが現実的です。
そのうえで、継続的な分析が必要となった段階では、データを一元的に管理・活用できるデータ基盤を整えることが重要です。基盤を整えることで、部署やツールごとに散在していたデータを統合でき、分析の効率化や迅速な意思決定に繋がります。
3.傾向把握のための分析を行う
収集したデータをもとに分析を進める際は、まず顧客を属性や購買行動などの基本的な観点で分類し、全体の傾向を把握することから始めます。性別・年齢・購買金額・購入頻度・商品カテゴリ・チャネルなどを基準にセグメントを分け、それぞれにどのような行動パターンが見られるのかを定量的に分析します。
例えば「月に1万円以上購入している30代女性」や「購入頻度は高いが直近3か月は離脱傾向にある顧客層」など、仮説ベースで複数のセグメントを定義し、パフォーマンスや傾向を比較することで、注力すべき顧客像や潜在的な課題を浮き彫りにできます。
特にロイヤル顧客については、購買行動だけでなく、利用頻度・購入継続性・心理的関与度といった複数の軸を組み合わせて定義することで、表面的な数値では捉えきれない「顧客の価値」をより正確に把握することが可能です。
この段階では、因果関係の解明よりも、次の深掘りフェーズに向けた仮説の土台となる構造的な傾向の把握が重要です。可視化された傾向は、インサイト探索や施策立案に繋げることができます。
4.顧客インサイトを掴むための分析を行う
ここでは、数値に現れない心理や動機といった「顧客インサイト」を明らかにすることで、より深い顧客理解に繋げるための分析を行います。
まずは、自社のビジネス成果と直結するテーマを定め、成果に貢献していると考えられる顧客をセグメント分析の結果から抽出します。例えば「商品の継続利用率の向上」がテーマの場合、リピート率が高い顧客や短期間でロイヤル化している顧客などが分析対象になります。
次に、対象顧客の属性データ・行動データ・購買データを時系列で整理し、あらゆる接点で得た情報を統合して「顧客カルテ」として可視化します。これにより、行動の変化や各接点での反応を立体的に捉えることができ、顧客の変化や傾向をより具体的に理解できるようになります。
例えば「ある商品の購入を機に購買頻度が増え、関連するセミナーへも参加し始めた」といった変遷が見られた場合、背後には何らかの心理的変化が生じている可能性があります。
こうした行動の背景にある動機や価値認識を深掘りする手段として、インタビューなどの定性的アプローチが有効です。実際の顧客の声を通じて、何に価値を感じたのか、何がきっかけで行動が変わったのかといった、数値では見えづらい「人」としての顧客像を捉えることができます。
行動データと心理データを組み合わせ、仮説と検証を繰り返すことで、顧客の価値観や行動の背景への理解が深まり、より正確な顧客理解へと繋がります。
5.分析結果をもとに施策を実行する
顧客理解を通じて把握した傾向やインサイトは、実際のマーケティング施策へと反映することで初めて意味を持ちます。行動・心理の両面から得た情報をもとに、顧客の状態やニーズに合わせた具体的なアプローチを設計・実行していくフェーズです。
具体的な施策例として、下記のようなものが考えられます。
- ロイヤル顧客に対する、継続的な利用価値を高めるキャンペーンや優待施策
- 離脱傾向のある顧客に向けた、障壁の解消や再興味喚起を狙ったコミュニケーション
- LTVの高い顧客群の行動やニーズをベースにした、新たなターゲット層への訴求強化
- 定性調査から得た価値観に沿った、クリエイティブ・メッセージの再設計
重要なのは、分析結果に基づいて「どのような価値を、どのように届けるか」を顧客視点で設計することです。単にセグメントを分けるだけでなく「なぜそうした行動に至ったのか」「どのような期待を抱いているのか」といった背景を理解し、的確なコミュニケーションや施策に落とし込むことが成果に直結します。
また、施策は一度にすべてを実行するのではなく、実行可能性・インパクト・仮説の精度を軸に優先順位を定め、段階的に進めていきましょう。リソースを分散させず、着実に実行と検証を繰り返すことで、施策の再現性や改善スピードを高めることができます。
分析して終わりではなく、顧客理解を起点にした実践的なアクションへと繋げていくことが、価値提供の精度を高める鍵となります。
EVERRISEによる分析支援
弊社EVERRISEでは、分析業務を支援するサービスを提供しています。
自社開発のCDP(カスタマー データ プラットフォーム)を提供してきた知見を活かし、分析基盤の構築から、分析・施策の実行までを一気通貫でサポートします。
- 分析基盤の構築支援
- 分析に不可欠なCDPやクラウドサービスを選定し、目的に応じたコスト効率の高い基盤を構築します
- 既存のデータ構造や業務フローを踏まえた設計も可能です
- 分析・施策の実行支援
- KPI設計、データ分析、施策の企画・設計・運用までを一貫してサポートします
- 分析リソースが不足している企業でも、成果に繋がる施策に集中できる体制を構築します
大規模なプロジェクトを前提とせず「今どこに課題があるのか」「何から始めるべきか」を整理しながら、次の一歩を描けるように伴走します。
本格的なご相談の前にまずは軽い壁打ちから、貴社の状況に合わせた最適な進め方を一緒に考えませんか。
支援内容について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。具体的な事例をもとに、支援内容の詳細を紹介しています。