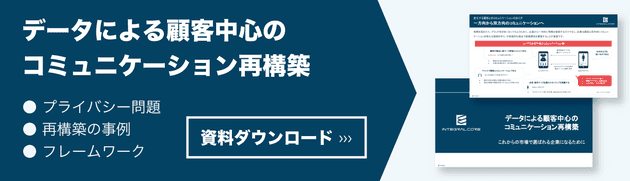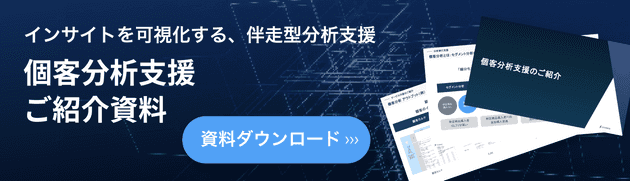取引の履歴や売上情報などの購買データの分析は、マーケティング活動の出発点となる基本的な取り組みです。
しかし、購買データだけでは「なぜその商品が売れたのか」「どういった顧客がどのような背景で購入したのか」といった深い洞察までは得られません。購買データと顧客データを組み合わせることで「誰が・なぜ・どのように」購入しているのかという文脈まで捉えることが可能になります。
本記事では、まず購買データのみを用いた分析の概要と限界について整理したうえで、購買データと顧客データによって実現できる高度な分析施策への活用例を紹介します。
購買データ分析とは
購買データとは、生活者が実際に商品やサービスを購入した際の記録や履歴を指し、一般的に「取引データ」「商品データ」の2つに分けられます。
それぞれのデータの内容と具体例は下記のとおりです。
| 取引データ | 商品データ | |
|---|---|---|
| 内容 | 「いつ」「どこで」「何を」「いくらで」購入したのかを1回の購入ごとに記録する | 商品IDやカテゴリ単位で、どの商品がどれくらい売れているかを集計する |
| 具体例 |
・購入日時 ・取引ID ・店舗・ECサイト情報 ・購入商品 ・数量 ・販売価格 ・支払い方法 |
・販売数量 ・売上金額 ・返品・交換数 ・併売情報 ・在庫推移 ・商品レビュー |
購買データを分析することで、よく売れている商品・購買が活発になるタイミング・商品同士の併売パターンなど、商品単位や取引単位での購買傾向を明らかにできます。
購買データ分析を行うメリット
売場・商品配置の最適化に繋がる
購買データの分析は、顧客の購買傾向や商品同士の関連性を可視化し、売場や商品配置の最適化に利用できます。これにより、メーカーはデータに基づく説得力のある商品提案を、小売は販売機会を最大化するための商品陳列の戦略を構築できます。
実店舗の場合、店舗ごとの購買データを分析することで、売れ筋商品をより目立つ場所に陳列する、併売傾向にある商品を近くに配置するなど、棚割や売場設計に活用できます。例えば「A商品は特定店舗でまとめ買いされる傾向がある」という結果が出た場合、陳列量を増やして売場面積を広げるといった施策が考えられます。
ECサイトの場合も、購買履歴や閲覧履歴から商品同士の関連性を明らかにすることで「この商品を買った人は、こちらの商品も購入しています」といったレコメンド表示や、売れ筋商品の特集枠の設置といった施策に利用可能です。ページ内での露出強化や購入導線の改善により、顧客単価の向上が期待できます。
実店舗では棚割や売場改善、ECサイトではレコメンドや導線設計といったように、チャネルごとに購買データを活用することで、それぞれの特性に応じた売場・商品配置の改善を、再現性・精度の高い形で実現可能です。
商品開発に活かせる
購買データを分析することで「どの商品が・いつ・どこで売れたのか」「どの商品同士が一緒に購入されやすいのか」といった傾向を把握でき「いつ・どのような商品を開発すべきか」「既存商品をどのように改良すべきか」といった商品戦略のヒントが得られることがあります。
例えば、健康志向の商品Aと商品Bが同時に購入される傾向が強いことが判明した場合、これらを組み合わせたセット商品の企画や、同じニーズを意識した新シリーズの開発などに繋がります。
業務効率化・コスト削減を実現できる
購買データの分析は、マーケティング施策だけでなく、在庫管理や物流計画の効率化にも活用できます。実店舗・ECサイトのいずれにおいても、需要予測の精度を高めることで、欠品や過剰在庫の防止、発注・配送の最適化が可能となります。
実店舗の場合、店舗ごとの購買データをもとに地域特性を把握し、需要の高い地域には在庫を多めに、需要が低い地域には抑えめに商品を配送するなど、拠点別の発注量の調整に活かせます。その結果、売れ残りや欠品リスクを低減しつつ、物流コストと在庫保管コストの削減が可能です。
ECサイトにおいても、エリア別・時期別の購買傾向を時系列で分析することで、セールや季節要因による需要の波を予測し、倉庫ごとの在庫調整や自動補充のロジックに反映させることができます。特に取り扱い商品が多いECサイトでは、運用工数の削減と在庫最適化の両立に繋がります。
購買データ分析の代表的な手法
実店舗とECサイトのそれぞれの観点から、購買データ分析の代表的な手法と活用例を紹介します。
バスケット分析
バスケット分析とは、1つの購買行動の中で一緒に購入される商品の組み合わせを明らかにする手法です。購買データに含まれる注文履歴をもとに、商品の組み合わせパターンや関連性を可視化することで、売場作りや商品提案に役立てることができます。
例えば実店舗では、併買情報をもとに「どの商品を近くに陳列すると売上が伸びるか」などの棚割改善に利用できます。「お弁当とお茶の併買率が高い」ことが分かれば、それらを同じ棚や導線上に配置するといった改善が可能です。
ECサイトでも「スマートフォンケースと保護フィルムが同時に購入される頻度が高い」ことが判明した場合、これらを対象にしたレコメンド・セット割引施策を実施することで、顧客単価の向上が期待できます。
このように「Aを購入した人はBも購入しやすい」といった購買傾向をもとに、クロスセル施策や関連商品のセット提案など、店舗・ECサイトを問わず販促施策に活用できます。
トレンド分析
トレンド分析とは、購買データを時間軸で捉え、売上や販売数量の増減傾向を把握する手法です。月別・曜日別・時間帯別などの購買動向に加え、季節やイベントに伴う需要の変化を明らかにできます。
例えば、過去の購買データから「6月後半に炭酸飲料の売上が急増する」傾向が分かれば、実店舗では販促物の設置や発注量の調整に、ECサイトでは特集ページの作成や広告配信の最適化に活用可能です。これにより、売上の最大化と欠品リスクの回避に繋がります。
トレンド分析は、需要予測やプロモーション時期の最適化など、売上最大化に向けた戦略設計に欠かせない分析手法です。
ABC分析
ABC分析とは、売上や利益への貢献度の合計をもとに商品を3つのランクに分類し、管理や施策の優先度を明確にする手法です。具体的には、下記のようにランクを分けます。
- Aランク:売上の大部分を占める商品
- Bランク:中程度の商品
- Cランク:売上貢献度が低い商品
例えば実店舗では、Aランクの商品には棚の陳列スペースを広く確保し、Cランクの商品は在庫数を調整するなどの対応によって、棚割りの最適化や在庫コストの削減が可能となります。
ECサイトでは、Aランクの商品を中心に広告配信やレコメンド設定を行うことで、流入数の増加や購入率の向上が期待できます。Cランクの商品は、プロモーション対象から外したり、掲載の優先度を下げたりすることで、運用コストの削減やユーザーの離脱防止に繋がります。
このように、ABC分析は限られた売場・人員・広告費などのリソースを、最も売上に貢献する商品に集中させるための基本的な分析手法として、メーカー・小売を問わず広く利用されています。
ただし、売上のみを指標に判断すると、重要な機会を見落とすリスクもあることに注意が必要です。単純な売上順位だけを見るのではなく、商品ごとの役割や販売文脈も含めた慎重な判断が求められます。
購買データ分析の限界
購買データの分析によって、売れ筋商品の把握・併売傾向の発見・時系列での需要変動の予測など多くの示唆が得られ、売上やコストの改善に繋げているケースも少なくありません。
しかし、なぜその購買が起きたのかといった背景や、顧客の行動を左右する要因については、購買データだけでは十分に把握することができません。
例えば、POSデータやECサイトのカート情報からA商品の売上が伸びていることが掴めた場合でも「どのような属性の顧客がリピートしているのか」「最終的に購買の後押しとなったものは何か」までは読み取れません。実店舗・ECサイトのいずれにおいても、購買行動は数値として記録されますが、行動の理由や心理までは捉えられず、商品の支持理由や購入動機を正確に理解するのは困難です。
会員システムやポイントシステムなどにより顧客を一意に識別できる情報があれば、購買データに顧客IDや属性情報を組み合わせた分析が可能となります。具体的には、下記のような傾向が明らかになることがあります。
- 「30代女性がA商品を定期的に購入している」
- 「初回購入者のうち、リピートしているのは共働き家庭が多い」
- 「離脱者は特定の年代・地域に偏っている」
こうした具体的な傾向を把握することで、離脱要因の仮説検証や、より正確なターゲティング施策の立案に活かすことができます。
購買データと顧客データを組み合わせるメリット
購買データと顧客データを組み合わせることで「誰が・なぜ・どのように」購入しているのかといった、顧客行動の背景や意図まで把握できるようになります。
例えば「40代男性は月初の金曜夜にビールとおつまみをまとめ買いする傾向がある」「共働きで買い物時間が限られる30代女性は時短調理食品を定期購入することが多い」といった購買パターンを把握できれば、タイミングやチャネル、訴求メッセージまで含めた個別最適な施策設計が可能です。
また、深い顧客理解をもとに、高い反応を示す層の共通点を抽出して類似ターゲットを発見することや、離脱傾向のある顧客に対する予防的アプローチなども可能になり、マーケティング施策の精度・再現性の向上が期待できます。
購買データに顧客データを組み合わせて分析することで、単なる売上の把握にとどまらず、顧客を軸にした戦略的なマーケティングの実行が可能となります。
関連:顧客理解を深める5つのステップ|行動と心理の両軸から顧客を捉える方法
購買データと顧客データによる分析の進め方
購買データと顧客データを組み合わせた分析は、下記の手順で進めていきます。
- KPIを設計する
- 傾向把握のための分析を行う
- 顧客インサイトを掴むための分析を行う
- 分析結果をもとに施策を実行する
1.KPIを設計する
分析のスタートとなるのがKPIの設計です。ビジネスゴール・現状の課題を整理したうえで、何を測定すべきかを明確にしましょう。例えば「購買単価を上げたい」といった目的がある場合、平均購買単価・高単価商品の購入割合・併売による客単価などがKPIの候補になります。
KPI設計時には、構成要素となるデータソースの調査・特定と、それらを支える統合環境の整備が必要です。購買行動・顧客属性・チャネル別実績など、複数の視点を前提とした指標を算出するためには、POSデータやECサイト上の行動データ、会員情報などのデータを統合・連携し、分析しやすい形に整備する必要があります。
こうした統合データをもとに、ダッシュボードを構築しておくことで、部門をまたいだKPIの可視化が可能になり、指標の定義の統一やレポート作成・集計作業の工数削減にも繋がります。
KPI設計では、単に数値を設定するだけでなく、それを「どのデータから、どのように導出し、誰が見るのか」までを含めて設計することが、実行可能な分析を実現するうえで重要なポイントです。
関連:KGI・KPIとは?企業別の事例と設定手順、KPIツリーの作り方
2.傾向把握のための分析を行う
KPI設計後に、属性・購買金額・購入頻度・商品カテゴリ・チャネルなどを切り口に顧客をセグメントに分け、それぞれにどのような行動パターンが見られるのかを定量的に整理します。
例えば「月に1万円以上購入している30代女性」や「購入頻度は高いが直近3ヶ月は離脱傾向にある顧客層」など、仮説ベースで複数のセグメントを定義し、それぞれの傾向やパフォーマンスを比較することで、注力すべき対象や課題を明確にできます。
特にロイヤル顧客については、購買行動だけでなく、利用頻度・購入継続性・心理的関与度といった複数の軸を組み合わせて定義することで、より戦略的な顧客理解と施策立案が可能になります。
この段階では、明確な因果関係を導き出すことよりも、仮説を立てるための事実を幅広く捉えることが重要です。「何が起きているのか」といった傾向を構造的に把握することで、次のフェーズでの深掘りや施策立案に繋げることができます。
3.顧客インサイトを掴むための分析を行う
ここでは、数値に現れない心理や動機といった「顧客インサイト」を明らかにするための分析を行います。
まずは、自社のビジネス成果と直結するテーマを定め、成果に貢献していると考えられる顧客をセグメント分析の結果から抽出します。例えば「商品の継続利用率の向上」がテーマの場合、リピート率が高い顧客や短期間でロイヤル化している顧客などが分析対象になります。
次に、対象顧客の属性データ・行動データ・購買データを時系列で整理し、あらゆる接点で得たデータを統合して「顧客カルテ」として可視化します。これにより、行動の変化や各接点で与えた影響を立体的に捉えることができます。例えば「ある商品の購入を機に購買頻度が増え、関連するセミナーへも参加し始めた」といった変遷が見られた場合、心理的な変化が生じた可能性があります。
こうした行動の背景にある動機や価値認識をより深掘りするための手段として、インタビューなどの定性的アプローチが有効です。実際の顧客の声を通じて、何に価値を感じたのか、何がきっかけで行動が変わったのかといった、数値では見えない気付きを得ることができます。
定量データと定性データを組み合わせて仮説と検証を繰り返すことで、顧客の価値観や行動変化を具体的に把握でき、深層的なインサイトの発見に繋がります。
4.分析結果をもとに施策を実行する
顧客インサイトを把握したあとは、その知見をもとに実際のマーケティング施策へと落とし込むフェーズに入ります。例えば、リピート促進・アップセル提案・離脱防止・セグメント別キャンペーンなど、目的や顧客ごとの特性に応じたアプローチを設計します。
重要なのは、分析で得られた顧客インサイトを踏まえ、それに応えるアプローチを設計することです。
例えば、継続利用率の高い顧客の分析から「ある商品を通じて日々の生活に楽しさや安心感を得ている」ことが見えてきた場合、その価値をさらに高めるような商品提案や体験機会を提供することで、顧客との関係強化に繋がります。離脱傾向のある顧客に対しては「なぜ使われなくなったのか」という背景を踏まえたうえで、障壁を取り除く施策や興味を再喚起するアプローチが有効です。
施策は実行して終わりではありません。効果検証によって仮説の精度を高め、成功パターンとしてナレッジ化し、次回以降の施策設計の質とスピードを向上させていくことが重要です。顧客の変化に応じてPDCAを継続的に回すことが、価値提供の精度を高める鍵となります。
また、施策の効果を高めるには、継続的な実行に加えて、顧客視点に立ったコミュニケーション設計を一貫して行うことが不可欠です。そのような取り組みを仕組み化することで、施策の質を継続的に高めていくことが可能になります。
データを使った顧客中心のコミュニケーションを構築する手順や注意点について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。事例を交えて、具体的に紹介しています。
無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために
EVERRISEによる分析支援
弊社EVERRISEでは、分析業務を支援するサービスを提供しています。
自社開発のCDP(カスタマー データ プラットフォーム)を提供してきた知見を活かし、分析基盤の構築から、分析・施策の実行までを一気通貫でサポートします。
- 分析基盤の構築支援
- 分析に不可欠なCDPやクラウドサービスを選定し、目的に応じたコスト効率の高い基盤を構築します
- 既存のデータ構造や業務フローを踏まえた設計も可能です
- 分析・施策の実行支援
- KPI設計、データ分析、施策の企画・設計・運用までを一貫してサポートします
- 分析リソースが不足している企業でも、成果に繋がる施策に集中できる体制を構築します
データ整備や基盤構築が完了している企業さまは「分析支援のみ」や「特定施策のスポット支援」でのご依頼も可能です。貴社の状況やご要望に合わせて、柔軟に対応いたします。
本格的なご相談の前にまずは軽い壁打ちから、貴社の状況に合わせた最適な進め方を一緒に考えませんか。
支援内容について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。具体的な事例をもとに、支援内容の詳細を紹介しています。