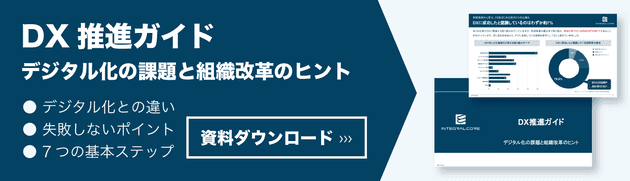DX(デジタルトランスフォーメーション)は経済産業省が2018年にガイドラインを公開、また多くのメディアに取り上げられ、社会に浸透しているキーワードとなりました。
すでにDXの取り組みを進めていたり、DX推進をする部署にアサインされた方も多いかと思います。しかし、DXという言葉を聞いたことがあっても明確に説明できない方もいるかもしれません。
DXの推進において、自社ではどのようにDXを定義し取り組むかを決めて動くことが重要です。この記事では、DXとはなにか、海外(欧米)と日本におけるリサーチ会社やコンサルティング会社のDXの定義、国内外の定義の違いについてご紹介します。
DXの言葉の意味
Digital Transformationの「Trans」の部分を英国圏では「X」と略すことから、「DX」と表記されます。
「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念が始まりで、2004年にスウェーデンのウメオ大学教授のエリック・ストルターマン氏の「Information Technology and The Good Life」という論文で初めて提唱されました。論文では次のような特徴を提示しています。
エリック・ストルターマンによる定義
- DXにより、情報技術と現実が徐々に融合して結びついていく変化が起こる。
- デジタルオブジェクトが物理的現実の基本的な素材になる。例えば、設計されたオブジェクトが、人間が自分の環境や行動の変化についてネットワークを介して知らせる能力を持つ。
- 固有の課題として、今日の情報システム研究者が、より本質的な情報技術研究のためのアプローチ・方法・技術を開発する必要がある。
発表当時は「デジタルは大衆の生活を変える」というような概念的な論文で、今後の研究へのアプローチ・方法論を述べた内容でしたが、スマートフォンの急速な普及による消費者行動変化などがあり、近年注目されるようになりました。
また、ビジネス用語としては定義や解釈があいまいではあるものの、おおむね「企業がITのテクノロジーを用いて、事業の業績や対象範囲を根底から変化させる」という意味合いで用いられています。
海外(欧米)におけるDXの定義
海外(欧米)におけるDXの定義は、主に以下の3つに分けられます。
- ガートナーの定義
- マッキンゼー・アンド・カンパニーの定義
- デロイトトーマツの定義
ガートナーのDXの定義
ガートナー(Gartner)社は世界有数のIT分野を中心としたリサーチ・アドバイザリを行う企業です。ガートナーは「デジタルビジネス」という概念を用いて、企業内のIT利用を3段階に分けています。
ガートナー社による定義
- 業務プロセスの変革
- ビジネスと企業、人を結び付けて統合する
- 仮想と物理の世界を融合して人/モノ/ビジネスが直接繋がり、顧客との関係が瞬時に変化していく状態が当たり前となる
ガートナーはこの第3段階の状態をデジタルビジネスと呼び、「仮想世界と物理的世界が融合され、モノのインターネット(IoT)を通じてプロセスや業界の動きを変革する新しいビジネスデザイン」と定義している。 また、このデジタルビジネスへの改革プロセスを「デジタルビジネストランスフォーメーション」と定義している。
ガートナーは、製品やサービスをデジタル化するだけでなく、デジタルを利用してビジネスモデルを変革する観点でDXを定義しています。
マッキンゼー・アンド・カンパニーのDXの定義
マッキンゼー・アンド・カンパニー(McKinsey & Company, Inc.)は世界最大規模の経営コンサルティングファーム企業です。 マッキンゼーではDXを次のように定義しています。
- 包括的なデジタル変革: 組織の構造変革におけるデジタル活用、デジタルを軸にした戦略と抜本的な組織変革の推進
- 顧客体験のデジタル化: デジタル活用による顧客ジャーニーの再構築、デジタルマーケティングやパーソナライゼーションを通じて顧客の囲い込み、啓蒙
- オペレーションの弾力性: オペレーションでのアナリティクス活用 (例:予防保全、生産性改善)による弾力性の強化やバックオフィスのプロセスの最適化・自動化
- 新規ビジネス構築: デジタル技術を活用した新規ビジネスの立上げや新規顧客セグメントの開拓
- スキル再教育と組織能力構築: デジタルに必要な組織能力構築、またそのための社内人材のスキル再教育、デジタル人材が活躍できる制度や仕組みの構築
- 組織全体の敏捷性: アジャイルオペレーティングモデルの導入、必要な仕組みの構築
- コアテクノロジーの近代化: クラウド・API 技術の活用、ITコストの最適化、データアーキテクチャーやデータ変革の実行
自社の中で、DX のどの塊が短期的・中長期的に重要になっていくのかについて、共通認識を持った上で、DX の取り組みを実施することが望ましい
マッキンゼーは組織改革やビジネス構造をデジタル化する文脈でDXを定義しています。また、組織に関する部分で一歩踏み込んでデジタル人材育成を推進についても触れています。
関連:DX人材の育成に必要な適性と6つのスキル、これからの時代に必要な組織作り
デロイトトーマツのDXの定義
デロイトトーマツ(Deloitte Tohmatsu Consulting LLC)は世界最大の会計事務所であり、経営戦略、M&AやITアドバイサリーなどを提供する世界最大級のグローバル経営コンサルティング企業です。 デロイトトーマツではDXを次のように定義しています。
デロイトトーマツのDXは、デジタルエンタープライズとなることを意味します。 デジタルエンタープライズは、データとテクノロジーを活用して、何を提供するのか、どのように販売し(顧客と関わり)、どのように届けるのか、そしてどのように組織を運営するのか、といったビジネスモデルのあらゆる側面を継続的に進化させる企業のことを指します。 また、デジタルマチュリティ(デジタル化の成熟度)を促進する要素を7つのデジタル・ピボット(デジタル化に向けた取り組み・軸)として定義し、その実践を提唱しています。 基礎的なピボットから着手することを推奨し、その実装に目途がついたら次は、1つの部署に対象を絞ってこれらのピボットを適用し、包括的な変革に取り組むべきと述べています。
「企業のデジタルマチュリティ(デジタル化の成熟度)向上を促進する7つのデジタルピボット」
- 柔軟で堅牢なインフラストラクチャー
- データ活用の熟達
- デジタル人材のオープンタレントネットワーク
- エコシステム全体への積極的な関与
- インテリジェントなワークフロー
- 一元化されたカスタマー・エクスペリエンス
- ビジネスモデルの適応力
より良い顧客との関係構築をデータやテクノロジーを活用し、それを提供するために組織やビジネスモデルをデジタルで進化させていくという点でDXを定義しています。また、独自の企業のデジタル化の成熟度を評価する段階的な要素を定義しており、企業が取り組むべきDXの道筋を示しています。
なお、DXと似た言葉に「デジタル化」がありますが、両者の意味は異なります。DXとデジタル化の違いについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。
関連:DXとデジタル化の本質的な違い|部門別の業務例とDX推進のポイント
日本におけるDXの定義
日本におけるDXの定義は、主に以下の2種類があります。
- IDC Japanの定義
- 経済産業省の定義
IDC JapanのDXの定義
IDC はIT・通信分野に関する調査・分析、アドバイザリ、イベントを提供するグローバル企業です。 日本法人であるIDC Japanは、ITプラットフォームの概念を用いてDXを次のように定義しています。
企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォームを利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること。
ITプラットフォーム 第1プラットフォーム:メインフレーム/端末システム 第2プラットフォーム:クライアント/サーバーシステム 第3プラットフォーム:クラウド・ビッグデータ/アナリティクス・ソーシャル技術・モビリティー
どのようなプラットフォームを使うべきかも具体的に示しており、市場や顧客の変化に対応しつつ、組織の変革に取り組みながら適切なプラットフォームを活用して、ユーザー価値を提供し市場の優位性を確立することとしてDXを定義しています。
経済産業省のDXの定義
経済産業省が2020年に策定した「デジタルガバナンス・コード2.0」では、DXを次のように定義しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
デジタル技術を用いてサービスやビジネスモデルを変革していくという文脈でDXを定義しています。 日本におけるDXは、経済産業省が2018年に発表したこの「デジタルガバナンス・コード2.0」のDXの定義をもとに語られることが多いです。また、経済産業省が提唱しているDXの定義はIDC Japanの定義を参考にしていると考えられます。
バイモーダルIT(守りのITと攻めのIT)
DXを考えるうえで、ガートナーが2015年に提唱したバイモーダルITという概念も参考になります。バイモーダルITは、効率化・コスト削減などを目的にした予測可能型のモード1と、差別化による利益拡大を目的とした模索型のモード2を使い分ける手法です。
- モード1:守りのIT、System of Record(SoR)
- 既存システムの再設計、コスト削減
- ウォーターフォール開発
- モード2:攻めのIT、System of Engagement(SoE)
- 新規事業を作り出すためのデザイン思考
- アジャイル開発
決済システムなど安全性を重視する開発では守りのIT(SoR)に寄せる形で実行し、顧客接点や新規ビジネスのためのシステムなど環境変化に対して柔軟に対応をする必要のある開発では攻めのIT(SoE)として実行するといった、守りのITと攻めのITを組み合わせて適切なIT活用を行うべきとする考え方です。
何を目的としたシステムなのかという話を抜きにしてウォーターフォール開発を否定する風潮もありますが、障害の発生が許されない守りのITにおいては完全に否定されるべきものではないと考えられます。
プロジェクトにあわせて守りのITに寄せるのか、攻めのITに寄せるのかを判断しながらそれぞれの長所を生かし、かつ徐々に攻めのITに対する比重を高めていくことが顧客に対する提供価値の向上および競合他社との差別化に繋がります。
攻めのDXで実現できることや攻めのDXの進め方について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
関連:「攻めのDX」とは?守りのDXとの違い、攻めのDX推進に必要なこと
日本のDXの現状と海外との違い
日本のDXは、現状のシステムの構成および運用における日本企業の”As Is”から語られることがあり、DXの手前の段階の課題が多くデジタル化やシステムの刷新自体をDXと捉えて取り組んでいる企業もあります。
経済産業省が2018年には発表したDXレポートにて次のように記載があります。
既存システムが、事業部門ごとに構築されて、全社横断的なデータ活用ができなかったり、過剰なカスタマイズがなされているなどにより、複雑化・ブラックボックス化 経営者がDXを望んでも、データ活用のために上記のような既存システムの問題を解決し、そのためには業務自体の見直しも求められる中(=経営改革そのもの)、現場サイドの抵抗も大きく、いかにこれを実行するかが課題となっている
このような現状に加え、DXの実現シナリオ(3ページ)では、DXの取り組みとしてそもそも2025年までにまずはシステムを刷新をすることを推奨する内容となっています。
また、ガートナーの2019年のサーベイ結果においても、日本のDXの現状について次のような記載があります。
世界の企業は、デジタル・ビジネスへの取り組みの「開始」段階から「拡大」段階へと移行しつつありますが、日本企業の4分の3以上は、デジタル化のプロセスに着手する「開始」段階を完了していません。また31%は、「デジタル・イニシアティブなし」および、デジタル・イニシアティブの「願望/目標」のみがあると回答しています。日本企業は、世界の企業の動きに追随できておらず、デジタル・ビジネスへの取り組みにおいて、世界との差が拡大しています。
引用:ガートナー 「日本企業はデジタル・ビジネス・イニシアティブにおいて 世界の企業に後れを取っているとのサーベイ結果を発表」
ガートナーは、DXをデジタル・ビジネスという表現を用いて三段階で定義していますが、日本の企業の多くがその1段階目の「開始」段階になくグローバルで見たときに大きく遅れをとっていることがわかります。
グローバル観点での遅れについてはすぐに取り戻すことは困難ですが、国内の企業間での競争においては、DXの障害となるレガシーシステムの刷新やそれに伴う組織改革、DXのスタート地点であるデジタルを活用した業務プロセスの改革に取り組むことが優位性を生むと考えられます。
ただし、今後のことも考えるとバイモーダルIT(守りのITと攻めのIT)も含め、先んじて取り組むことが可能な領域に対して攻めのITに取り組むべきだとも考えられます。
日本におけるDXを進める中での注意点
日本では、デジタル技術を提供する企業の目線でDXを捉え自社のサービスや製品の導入を勧めているケースが少なくありません。そのようなサービスや製品の一部はDXの1つのファンクションになる可能性はありますが、それらを導入すること自体がDXの取り組みとは言えません。
あくまで、自社の現状(As is)と目標(To be)を明らかにして自社にとってのDXを定義したうえで取り組むことが重要です。
DX推進の詳しい手順や失敗事例から学ぶ心構えや守りのDXと攻めのDXの間で起こる問題とその解決策について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。
無料資料:DX推進ガイド|デジタル化の課題と組織改革のヒント