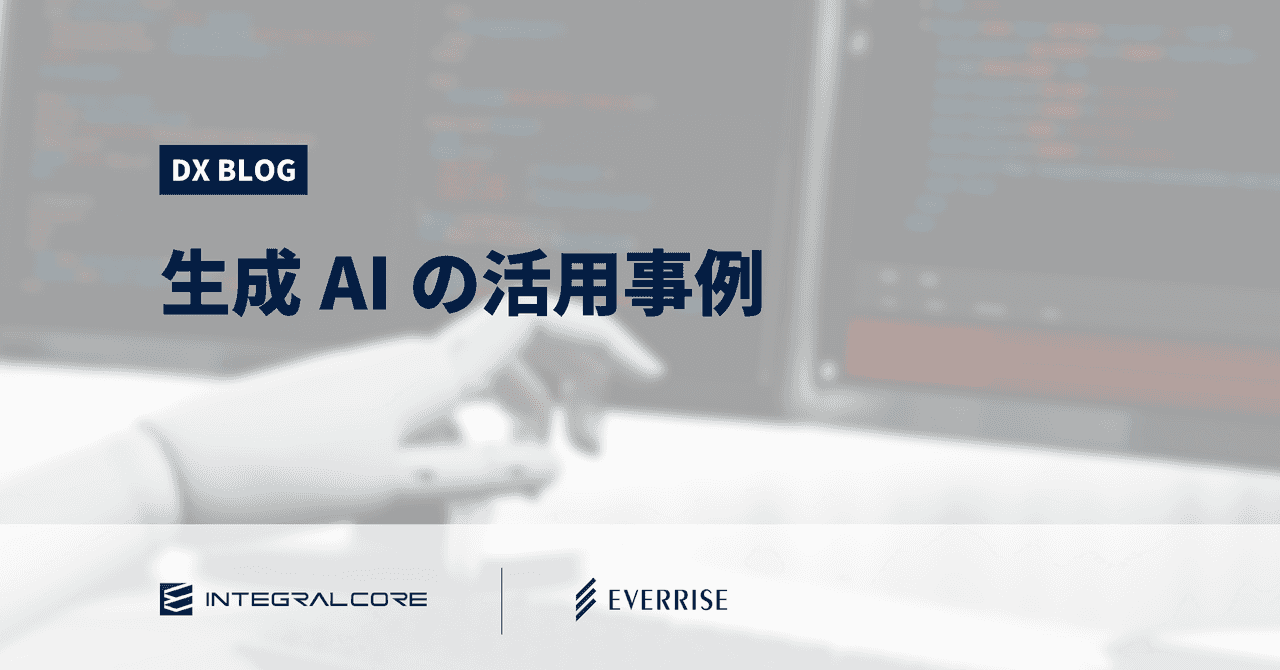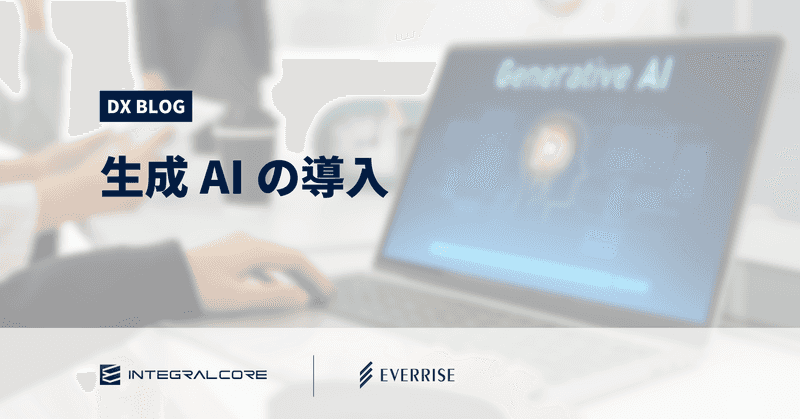生成AIは、膨大なデータを学習したAIが文章・画像・動画・音声といった新しいコンテンツを自動生成する技術です。従来のAIが得意としてきた「分析・予測」を超え、アウトプットそのものを生み出せる点が特長で、多くの企業が実務活用を進めています。
本記事では、生成AIの基本から導入メリット別の活用事例、活用時のリスクと対応策について紹介します。
生成AIとは
生成AI(Generative AI)とは、膨大なデータを学習したAIがコンテンツを自動生成する技術です。
従来のAIは、例えば「過去の売上データから来月の需要を予測する」「顧客を属性ごとに分類する」などの分析や予測を得意としてきました。生成AIは、学習した知識をもとに文章や画像など多様なコンテンツを自動的に生み出すことができ、従来の枠を超えて新たな価値や体験を創出します。したがって、生成AIは、企業の事業プロセスやタッチポイント(顧客接点)そのものを変革する可能性を秘めています。
生成AIが生成できる代表的なアウトプットは下記のとおりです。
| 生成領域 | 内容 | 主な活用例 |
|---|---|---|
| テキスト生成 | 自然な文章や会話を生成 |
・レポート作成 ・チャットボット応答 |
| 画像生成 | 指定条件に基づいた画像を生成 |
・商品イメージ作成 ・広告ビジュアル作成 |
| 動画生成 | 映像やアニメーションを生成 |
・プロモーション動画作成 ・教育用コンテンツ作成 |
| 音声生成 | 音声やナレーションを生成 |
・音声ガイド作成 ・ナレーション作成 |
生成AIを企業が活用するメリットと活用事例
生成AIの活用に着手し始めている企業が増えています。生成AIの導入目的は主に下記の3つに整理できます。
- 業務効率化・生産性の向上
- 顧客体験の向上
- 創造性・クリエイティブ作成の強化
業務効率化・生産性の向上
多くの企業では、資料作成や会議の議事録まとめ、調査データの整理といった定型業務に多くの時間を費やしています。そのため、本来注力すべき企画立案や顧客対応に割けられるリソースが限られるケースも少なくありません。その結果、組織全体の生産性が下がり、意思決定のスピードに影響を与える可能性があります。
生成AIは自然言語処理や要約生成に強みを持ち、大量の情報を短時間で整理・文書化し、下書きの自動作成が可能です。従業員は「作業」よりも「判断」や「提案」に専念できるようになり、業務全体のスピードと質の向上が期待できます。また、外部委託に依存していた業務の一部を内製化することで、コスト削減やROI(投資対効果)の改善や収益性の向上も期待できます。
生成AIの活用は単なる作業時間の削減にとどまらず、高付加価値業務への注力を促進し、組織全体の生産性と柔軟性を高めることに繋がります。
業務効率化・生産性向上観点での生成AI活用事例
業務効率化・生産性向上の活用事例を3つのテーマで紹介します。
- 文書作成・レポート業務の効率化
- 情報整理・リサーチ支援
- バックオフィス業務の自動化
文書作成・レポート業務の効率化の観点では、株式会社LIFULLの事例があります。
LIFULLは社内向けの生成AI活用を推進し、2023年10月から2024年3月までの半年間で合計20,732時間の業務時間創出に成功しました。社内調査によると、従業員の71.8%が生成AIを活用して業務効率化を実感しており、利用者の半数以上は業務の質の向上に繋がったと回答しています。活用シーンは文章・資料の作成や編集が最も多く、次いで調査・検索や情報整理などにも利用されています。
情報整理・リサーチ支援の観点では、パナソニック コネクト株式会社の事例があります。
パナソニック コネクトは自社向けのAIアシスタントサービスを導入しました。従業員は検索エンジンの代替としての利用や、戦略策定の基礎データ作成を主な目的に活用しました。社内アンケートの結果、1回あたり平均約20分の時間削減に繋がっていることが確認でき、日常的な調査・リサーチ業務の効率化に大きく貢献しています。
バックオフィス業務の自動化の観点では、ユニファ株式会社の事例があります。
ユニファは、岩手県北上市・神奈川県横須賀市・東京都狛江市の保育施設で生成AIを活用した実証実験を行いました。写真整理では、不適切写真の自動検出や園児ごとの写真枚数チェックを自動化し、数百〜数千枚の確認作業の削減を狙っています。また、書類作成では、箇条書きからの文章化や誤字修正、翻訳を支援することで保育者の事務負担軽減を実現し、子どもと向き合う時間の確保に取り組んでいます。
顧客体験の向上
顧客との接点は増えている一方で、一人ひとりの期待に十分応えられていないと感じる企業は少なくありません。結果として、顧客満足度やロイヤルティの低下を招くケースも見られます。
生成AIは、属性情報・購買履歴・行動データなどの顧客データをもとに、状況に応じた最適な提案やコミュニケーションを自動生成できます。顧客は「自分のために用意された体験」と感じやすくなり、満足度の向上やLTV(顧客生涯価値)の改善、解約率の低下といった成果が期待できます。また、カスタマーサポートの迅速化や待ち時間短縮によって顧客のストレスを軽減し、ブランドロイヤルティの強化にも繋がる可能性もあります。
生成AIを活用した顧客体験の向上は、ブランド価値や競争優位性の源泉となり、企業全体の成長に繋がります。
顧客体験の向上観点での生成AI活用事例
顧客体験向上の事例を2つのテーマで紹介します。
- パーソナライズ体験の提供
- 利便性の向上
パーソナライズ体験の提供の観点では、株式会社ぐるなびの事例があります。
ぐるなびは、モバイルオーダーサービスに生成AIを活用したチャットボットを導入しました。利用者が「さっぱりしたものが食べたい」「がっつり食べたい」といった抽象的な要望を入力するだけで、AIが最適なメニューを提案する仕組みを構築しました。その結果「メニュー選びの楽しみが広がった」などの声が寄せられるなど、体験満足度の向上に繋がっています。
同様に、株式会社ベネッセホールディングスの事例があります。
ベネッセホールディングスは進研ゼミの一環として、小学生向けに自由研究を支援する生成AIサービスをリリースしました。利用者が入力した興味や希望に応じて研究テーマの候補やアドバイスを返す仕組みを構築しました。アンケート結果では利用者の8割以上が「役に立った」と回答しており、新しい学習体験として高く評価されました。
さらに、株式会社ローソンの事例もあります。
ローソンは、テクノロジーとリアルの温かみを融合した未来型店舗「Real×Tech LAWSON」をオープンしました。該当店舗では、AIカメラを用いた行動解析によるパーソナライズ商品のレコメンドや、画像生成AIを活用した空間演出を導入し、来店のたびに新しい体験を楽しめる売場を実現しました。また、生成AIを搭載したコミュニケーションロボット「AI Ponta」が自然な会話で商品や地域情報を案内するなど、従来のコンビニ接客を超える新たなサービスを提供しています。
利便性の向上の観点では、株式会社ビズリーチの事例があります。
ビズリーチは、転職サイト「ビズリーチ」に生成AIを活用したレジュメ自動作成機能を導入しました。職種や業務内容を入力すると職務経歴書を自動作成できる仕組みで、求職者は短時間で質の高いレジュメを準備可能になりました。共同検証では、この機能を利用したレジュメが従来より高評価を得やすいことがわかり、スカウト受信数も平均約40%増加しました。これにより、求職者の負担軽減と企業側のマッチング精度向上が期待されています。
また、株式会社アダストリアの事例もあります。
アダストリアは、自社が展開する「グローバルワーク」「ニコアンド」などのブランドにおいて、生成AIを活用したチャットボットを導入しました。その結果、有人チャットの問合せ件数は最大で約50%削減され、チャットボットの自己解決率は88%を記録しました。結果として、顧客対応の効率化や顧客満足度の向上に繋がっています。
創造性・クリエイティブ作成の強化
生成AIは、従来の制作プロセスにおけるリソース・コストの制約を超え、多様な発想や表現を短時間で生み出す手段として注目されています。コピーやビジュアルの初稿生成から、キャラクター設定・物語構造の提案・参加型コンテンツ制作まで、幅広い活用が期待されています。
例えば、広告・ブランディングの分野では、AIキャラクターやバーチャルタレントの活用により柔軟な表現展開が可能になり、新しい顧客接点の創出やブランドイメージ刷新に繋がる可能性があります。また、体験型コンテンツを通じてユーザー自身が創造プロセスに関与できる仕組みを設けることで、インタラクティブな体験へと発展させることも可能です。
生成AIは、多様なアイデアを短時間で提示することで検討を加速させ、クリエイティブの「質」と「量」を同時に高めることが期待されます。結果として、企業の差別化やブランド力強化に繋がる手段となる可能性を秘めています。
創造性・クリエイティブ作成の強化観点の生成AI活用事例
創造性・クリエイティブ作成の強化に関する事例を3つのテーマで紹介します
- 広告・ブランド表現
- プロモーション施策
- 商品企画・開発
広告・ブランド表現の観点では、株式会社伊藤園の事例があります。
伊藤園は「お~いお茶 カテキン緑茶」のプロモーションでAIタレントを起用したCMを制作しました。「現在の自分」と「30年後の未来の自分」を自然に繋げる表現を生成AIで実現し、健康的で前向きなイメージを短期間で具現化することで、ブランドの先進性を強調しました。この取り組みをきっかけに多くのメディアから取材を受けるなど、業界内外で大きな注目を集めました。
プロモーション施策の観点では、アサヒビール株式会社の事例があります。
アサヒビールは、新商品「アサヒスーパードライ ドライクリスタル」のプロモーション施策として、画像生成AIを活用した体験型コンテンツ「Create Your DRY CRYSTAL ART」を展開しました。ユーザーが自身の写真やテキストを入力し「水彩画風」「アニメ風」などのスタイルを選ぶことで、オリジナルアートを生成できる仕組みです。消費者参加型のブランド体験を通じて、商品の認知拡大や購入意欲の向上を狙った例です。
商品企画・開発の観点では、セガサミーホールディングス株式会社の事例があります。
セガサミーホールディングスは、グループ会社であるセガ フェイブ Toysカンパニーにおいて、製品画像を学習させた画像生成AIとアンケート分析AIを導入しました。生成AIが既存デザインをもとに多様な新案を短時間で提示し、従来の100倍に相当する選択肢を創出することで、デザイナーはより創造的な業務に集中できるようになりました。また、数万件の自由記述アンケートから感情を含む洞察を抽出し、製品改善に活用することで、外注コストの削減と約80%の分析工数の削減に成功しました。
企業が生成AIを活用するリスクと対応策
生成AIを活用する際には、さまざまなリスクが伴います。主な3つのリスクと対応策を紹介します。
- 法務・コンプライアンスへの影響
- 顧客体験への影響
- 企業ブランド・社会的信用への影響
法務・コンプライアンスへの影響
生成AIが著作権で保護された情報や個人情報を入力・出力した場合、法令違反や契約違反に直結します。違反した場合、訴訟や制裁金といった直接的な法的責任に加え、取引停止などの事業リスクに発展する恐れがあります。
対応策としては、入力データの匿名化や機密情報の遮断、外部サービス利用時の契約条件の確認が必須です。また、法務部や情報システム部と連携し、最新の法規制やガイドラインに適合させた体制を維持することが重要です。
顧客体験への影響
生成AIが誤情報(ハルシネーション)や不適切な回答を出力する可能性があります。そのような情報が顧客に届けば混乱や不満を招き、解約や顧客離れに繋がる恐れがあります。
対応策としては、回答のレビュー体制や定期的な精度の検証体制を設けることが重要です。あわせて、顧客接点で利用するAIには、出典や根拠を示す機能を組み込み、透明性を高める工夫が求められます。
企業ブランド・社会的信用への影響
生成AIが差別的・攻撃的な表現や社会的に不適切と受け止められる内容を出力した場合、炎上やブランド毀損に繋がる恐れがあります。
対応策として、倫理面を含めたガイドラインを策定・徹底することが求められます。また、利用履歴を追跡できる監査体制を整え、万一の事態に備えて説明責任を果たせる準備をしておくことが重要です。
EVERRISEによる、AI活用支援
生成AIは、業務効率化から顧客体験の高度化、クリエイティブ強化まで幅広く活用できます。一方で、導入にはリスクも伴うため、戦略的かつ組織的な取り組みが欠かせません。
AI活用で重要となるのが、課題の明確化と仮説設定です。すぐに開発へ移るのではなく、PoC(概念実証)を通じて、実際の業務で活用可能な品質のアウトプットが得られるかを検証する必要があります。
特に生成AI活用では、保有データの状態や適用する課題・仮説によって成果の不確実性が大きくなるため、PoCを経て慎重に判断することが求められます。
弊社EVERRISEでは「AI活用戦略」の構築を支援するコンサルティングサービスを提供しています。初期の課題・仮説の設定からPoC、開発・運用まで一気通貫で支援が可能です。
まずは、生成AI活用における課題・仮説設定に向けた壁打ちから始めてみませんか。お気軽にご相談ください。