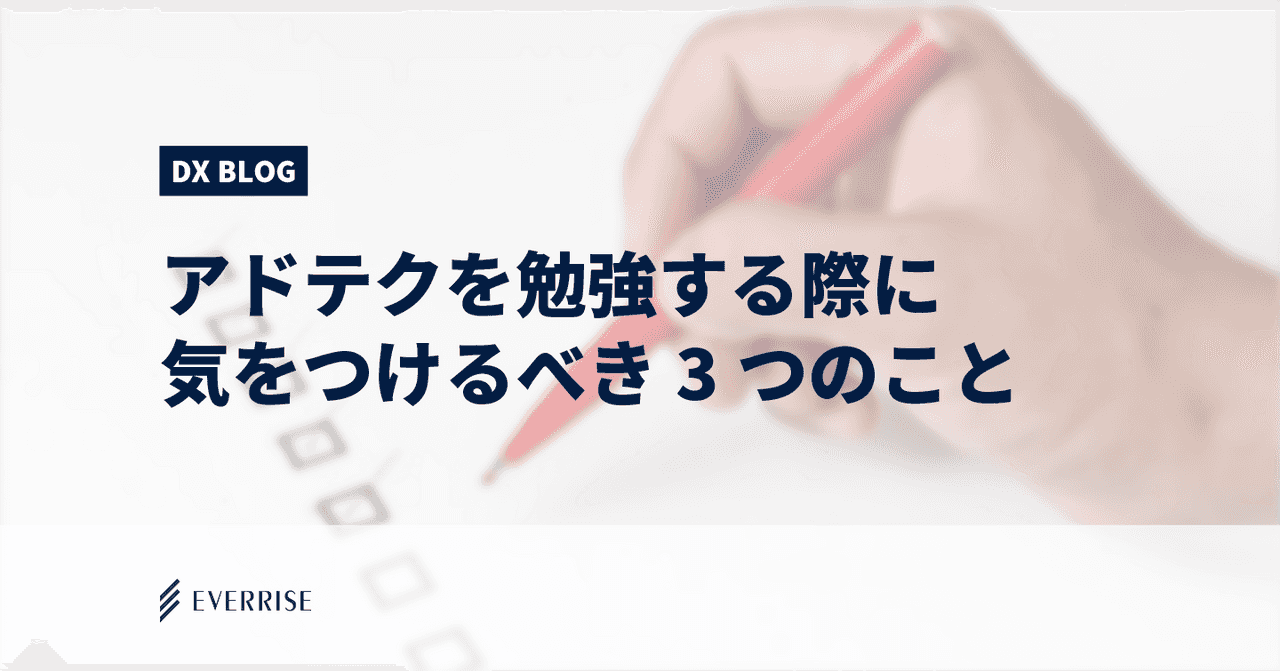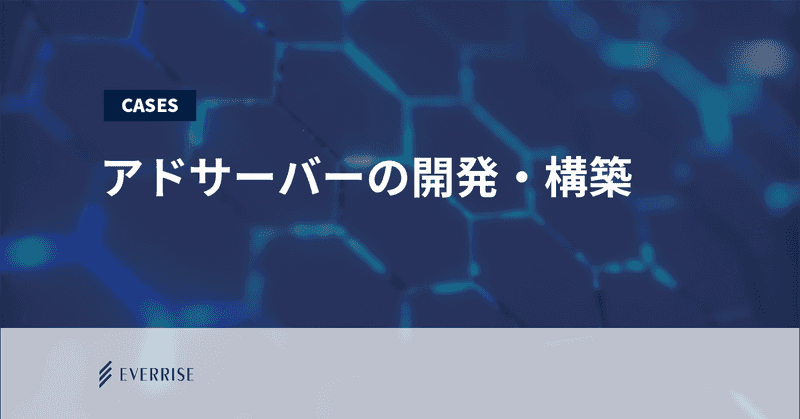本記事では、アドテクを勉強するにあたって気をつけたい点について紹介します。
アドテクはどんどん進化を遂げる中で、次々に新しい技術や用語が生まれています。そのアドテクの進化に追いつこうと勉強する際に気をつけたい点は以下の3つです。
- 流れの中で理解する
- 本当に正しい情報なのか
- それが一番新しい情報か
1つずつ私の経験をもとに書いていきたいと思います。
流れの中で理解する
例えば、「SSP」や「DSP」といった言葉を調べると、「最適化」「利益の最大化」「最適な広告配信」など、どちらも似た言葉が説明に出てきます。しかしこの二つの役割はまったく異なります。これを調べたアドテク初心者の私には違いを理解するのにとても時間がかかりました。他には、アドネットワークとアドエクスチェンジも似ていますし……。
違いをちゃんと理解するためのポイントは、「誰が」、「いつ」、「どのように」でした。その機能やシステムは誰がどのような時に使って(効果を発揮して)、どのように作用するのか理解することが重要です。用語を一つひとつ個別に考えるのでなく、実際の広告業務全体の流れで意味を捉えましょう!これがなかなか難しいんですが……。
本当に正しい情報なのか
分からないことを調べるとき、今圧倒的にスピーディーで手軽なのはインターネットでの検索ではないでしょうか。私も多くの情報をインターネットから得ています。
アドテク用語をインターネットを通じて検索して、多くのページを見ていく中で思ったことは、似たり寄ったりな記事が多い(コピペ含む)ということです。正解はあるわけなので、これは必ずしも悪いことではないのですが、アドテクの場合、コピペが多くさらに少しずつ間違っていたり、説明が不足していたりすることも多いのです。
初心者なりの感覚でしかありませんが、本当に理解していることを自分の言葉で説明している場合と、よく分かっていないけどとりあえず言葉を拾ってきてつなぎ合わせている場合とがあるように思います。後者の情報を信じていては大変です。なので、インターネットで調べる場合は、できるだけ沢山のページを見て、その情報は怪しくないか、どの情報を信じていいのかを常に疑ってかかる必要があります。アドテクの時に限らないですけどね。そしてできれば、分かっている人に確認したり(自分では理解したと思っても)、書籍もチェックしたりすることをおすすめします。
それが一番新しい情報か
最初にも述べたとおり、アドテクはめまぐるしい進化を続けています。インターネット上の情報や資料もどんどん古くなっていきます。正しい情報かどうかと同様に、それがいつ書かれた情報なのかも気にしなくてはなりません。
まとめ
情報が沢山あるからこそ、見極めが難しいなと感じながら日々勉強しています。
以上、アドテク初心者によるアドテク勉強のポイントでした。