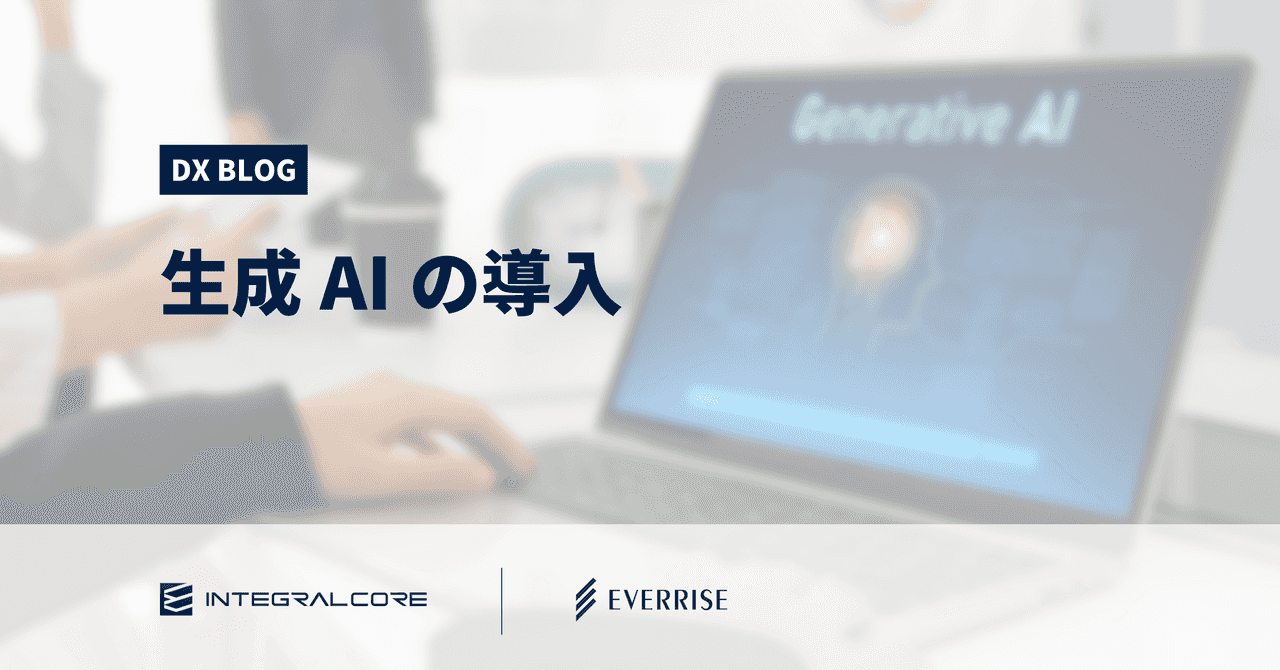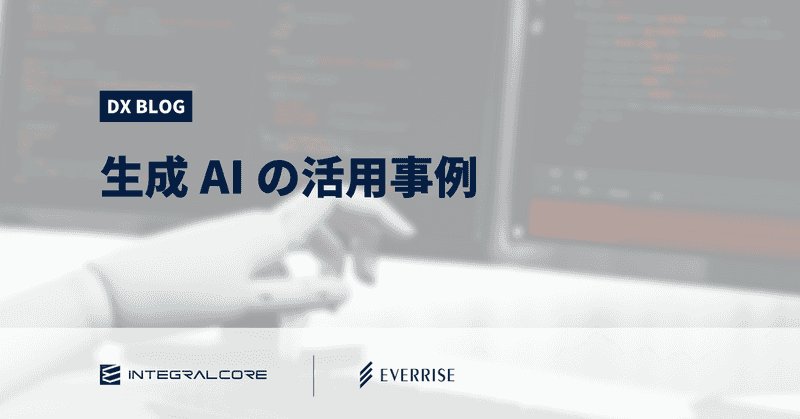生成AIの注目度が高まり、導入を検討する企業が増えている一方で、「PoCで止まってしまう」「全社展開の手前でつまずく」といった課題に直面する企業は少なくありません。導入効果を最大化するには、業務課題の特定からPoC・基盤整備・運用へと、段階的に広げていくことが不可欠です。
本記事では、生成AIの主要な適用領域と実現に求められる前提条件を整理したうえで、導入に向けたステップを解説します。また、全社展開の局面で多くの企業が直面する課題とその解決策についても紹介します。
生成AIの適用領域と実現に求められること
生成AIは、社内業務の効率化や顧客接点の高度化など、幅広い領域での活用が進んでいます。主要な活用領域と、それぞれの実現に求められる要件は下記のとおりです。
| 活用領域 | 具体的な活用例 | 実現に求められること |
|---|---|---|
| 営業・CRM支援 | 顧客属性や取引履歴をもとにした提案資料の自動生成 | 構造化データと非構造化データの統合 |
| カスタマーサポート支援 | 問合せチャネルごとの自動応答 |
・応対ログ形式に合わせたデータの構造 ・継続的な学習・チューニング |
| マーケティング・販促支援 | 特定施策実施後の効果レポートの自動生成 |
・顧客・商品データをもとにした構造設計 ・生成結果の品質管理 |
| ナレッジ共有・社内FAQ | 部門横断的な社内検索ポータルの構築 |
・社内ドキュメントの整備 ・アクセス権限を考慮したRAG設計 |
| 顧客対応チャットボット | 契約更新・支払いに関する手続きの自動案内 | 応答制御、言い回し・表現の調整 |
| パーソナライズCX構築 | 来店頻度に応じたクーポン配信やフォロー施策の自動化 |
・行動データの統合・管理 ・トリガーロジックの定義 |
| コンテンツ生成支援 | ホワイトペーパー・調査レポートの自動生成 |
・表現ルール・ブランドガイドラインの統合・管理 ・自動評価指標との連携 |
| VOC分析・インサイト抽出 | 顧客の声をもとにしたトレンド分析、改善点の抽出 | データ収集・分析基盤の整備 |
生成AIを使えば、データさえあれば生成AIが判断して良いアウトプットが出てくると期待をしたくなります。しかし、生成AIが適切なデータを扱える状態を作ること、それをもとに生成AIが適切なアウトプットを出すようにチューニングする作業が必要不可欠です。
生成AIの導入ステップとポイント
生成AIの導入は、データの状態やテーマにより、期待するレベルのアウトプットが出てくるか不確実性が高いため、まずはPoC(Proof of Concept:概念実証)にて評価をしたうえで、実際に利用できるかを判断する必要があります。
ここでは、上記の進め方で生成AIを導入する5つのステップと、それぞれで意識すべきポイントを整理します。
- 目的・適用領域・目標の設定
- 活用体制の整備
- PoC設計・評価
- ガバナンスの整備
- 実装・運用・改善
1.目的・適用領域・目標の設定
まずは、どのような課題に対して生成AIを導入するのかを明確にし、適用領域を決定することから始めます。例えば「問合せ対応に多大なリソースが割かれている」など具体的な課題が存在し、その解決を目的に導入を進めるのが一般的です。
一方で、生成AIの導入自体を目的化してプロジェクトが開始するケースも少なくありません。しかし、この場合は課題設定が曖昧になりやすく、PoCでの評価指標を適切に設定できず、次の段階に進めない可能性が高くなります。
生成AIの導入自体が目的化している場合でも、評価指標を設定できる課題をPoCとして定め、そのうえでプロジェクトを進める必要があります。
具体的な作業内容と検討観点の例は下記のとおりです。
| 作業内容 | 検討観点の例 |
|---|---|
| 業務課題の整理・活用領域の決定 |
・評価が行える課題設定となっているか ・既存業務に大きな影響を与えずに導入できるか |
| KGI・KPIの数値化 |
・短期・中期で測定できる指標か ・経営層に成果を説明できる形になっているか |
| 既存データ・システム環境の棚卸し |
・既存システムとの連携にどの程度改修が必要か ・データ品質が十分か |
この段階では、解決すべき課題・改善したい業務を具体的な数値目標に落とし込むことが重要です。例えば「問合せ対応の平均時間を10分から7分へ短縮する」といった形でKPIに紐付けることで、効果検証や投資判断の基準として利用できます。
複数の適用領域を検討する場合は、必要なリソースやインパクトの大きさを踏まえ、優先順位をつけて決定しましょう。
2.活用体制の整備
生成AIの導入は、活用する部署だけでなく、情報システムや法務といった関連部署を巻き込み、小規模でも機能する体制を整える必要があります。
具体的な作業内容と検討観点の例は下記のとおりです。
| 作業内容 | 検討観点の例 |
|---|---|
| ステークホルダーの役割整理 | ・責任範囲や意思決定権が曖昧になっていないか |
| 関連部署の担当者選出 | ・不必要な関係者・部署を巻き込んでいないか |
| 合意形成のプロセス設計 | ・意思決定フローが過剰に複雑化していないか |
最も重要なのは、責任の所在と意思決定の流れを明確にすることです。これにより、想定外の課題やトラブルが生じてもスムーズに判断・対応ができ、プロジェクトを計画通りに進めやすくなります。
3.PoC設計・評価
選定した領域で生成AIが本当に効果を発揮するのかを、小規模な検証を通じて確認するのがこの段階です。PoC(Proof of Concept:概念実証)は、単なる実験ではなく「実際に使えるか」「投資に見合う成果が出るか」を確かめる工程であり、その結果が本格導入の判断材料になります。
具体的な作業内容と検討観点の例は下記のとおりです。
| 作業内容 | 検討観点の例 |
|---|---|
| 検証テーマ・評価指標の設定 |
・ビジネス成果と直結しているか ・指標が測定可能で、曖昧さが残っていないか |
| 運用・拡張計画の方向性策定 |
・利用量の増加に耐えられる拡張性があるか ・拡張に必要な追加リソースやコストを把握できているか |
| 法務・セキュリティの事前確認 |
・セキュリティ要件や社内規程に準拠しているか ・外部サービス利用時の契約条件を確認しているか |
| 実証環境の整備 |
・利用者が操作しやすい環境になっているか ・本番環境への移行も視野に入れた構成になっているか |
| 検証実施・結果確認 | ・設定した指標に基づき成果を客観的に評価できているか |
PoCのポイントは、成功か失敗かを判断できる明確な基準を設けることです。まず、課題に対して適切な効果が得られているかどうか、例えば「1ヶ月で◯◯時間の工数削減」といったコスト観点での評価指標が必要です。
また、実際の利用で問題のないアウトプットかを判断するための指標、例えば「回答精度80%以上」とその評価方法を設定しておく必要があります。
4.ガバナンスの整備
生成AIの導入では、効果を出す仕組みづくりと同時に、リスクを管理し安心して利用できる環境を整えることが欠かせません。ただし、最初から大規模なルール体系を作る必要はなく、まずは最低限のルールやチェック体制を用意しておけば十分です。
具体的な作業内容と検討観点の例は下記のとおりです。
| 作業内容 | 検討観点の例 |
|---|---|
| データ利用ルールの設計 |
・現場で運用可能な簡易的なものになっているか ・解釈のブレが生じない表現になっているか |
| 監査ログ・利用履歴の設計 |
・保存期間やアクセス範囲が明確になっているか ・ログの記録粒度が十分か |
| セキュリティ・アクセス権限の設定 |
・機密度に応じてアクセス制御が設定されているか ・外部サービス連携時にも適切に制御できるか |
| 利用ポリシー・ガイドラインの策定 |
・現場の利用者に理解しやすい表現になっているか ・社内規程や就業規則と整合性が取れているか |
| リスク評価・コンプライアンス確認 |
・外部サービス利用時の契約条件や利用規約に抵触していないか ・誤回答や虚偽情報が出た際の検出・修正プロセスが用意されているか |
| 教育・研修の実施 |
・新入社員や異動者にも継続的に教育できる体制か ・研修効果を測定できる仕組みがあるか |
ガバナンス整備で最も重要なのは、現場が安心して利用できる環境をつくることです。ルールを厳しくしすぎると「使えない仕組み」になってしまいますが、逆に緩すぎると情報漏えいや法務トラブルに繋がります。そのため、例えば「顧客データの取り扱いは厳格に管理しつつ、一般的な文書作成では柔軟に利用できるように設計する」といった、メリハリのある設計が求められます。
また、生成AIは外部サービスを利用するケースも多いため、契約やライセンス条件、業界規制との整合性を事前にチェックしておくことも重要です。
5.実装・運用・改善
PoCや技術基盤の選定を経て、本格的に業務へ生成AIを組み込む段階です。このフェーズでは、単にシステムを導入するだけでなく、実際の業務プロセスにどのように取り入れ、成果を定着させるかが重要となります。
具体的な作業内容と検討観点の例は下記のとおりです。
| 作業内容 | 検討観点の例 |
|---|---|
| 運用フローの設計 |
・既存業務プロセスと無理なく統合できているか ・障害や不具合発生時の対応手順が定義されているか |
| 実装・業務への組み込み |
・従来業務からの移行負担が最小限になっているか ・導入前後のサポート体制を整備できているか |
| 効果測定・KPIモニタリング |
・導入目的に沿ったKPIが定期的に測定されているか ・KPIの達成度が改善サイクルに反映されているか |
| 継続改善の実施 |
・利用者からのフィードバックを収集できているか ・モデル更新を定期的に行える体制を構築できているか |
実装フェーズで最も重要なのは「導入して終わり」にしないことです。現場での利用実態を定期的にモニタリングし、KPIの進捗を確認することで、投資効果を継続的に示せます。特に生成AIは機能や性能の更新サイクルが短いため、モデルやツールを定期的にアップデートし、精度や安全性を高め続ける運用体制が欠かせません。
効果や課題を確認しながら改善を重ね、その成功事例をもとに導入範囲を徐々に広げることで、リスクを抑えつつ全社的な定着を進められます。
生成AI導入後の全社展開時に直面する課題
生成AIを特定領域に導入し一定の成果が得られた場合でも、その後の全社展開フェーズで新たな課題に直面するケースが少なくありません。
多くの企業が直面する代表的な課題が下記のとおりです。
| 課題 | 具体内容 |
|---|---|
| 現場への定着不足 | 部門ごとに使い方や期待値が異なり、仕組みはあっても浸透しない |
| ROIの可視化不足 | 投資対効果を経営層に説明できず、全社展開の意思決定が滞る |
| 運用コストの増大 | 利用範囲拡大でクラウドやAPI費用が膨らみ、予算計画を超過する |
| 適切なガバナンスの設計 | 必要な要素を考慮したガバナンスの設計が難しい |
このように、全社展開のフェーズでは技術面だけでなく、技術面よりも組織面・運営面の課題が顕在化しやすいのが実情です。
社内定着や人材育成、ガバナンスの見直しを計画的に進めると同時に、必要に応じて他社の取り組みや外部の知見を取り入れることが、全社的な成果に繋がります。
EVERRISEによる支援
弊社EVERRISEでは、適用領域の選定からPoC、基盤整備、運用、全社展開までを一気通貫でご支援する「AI活用戦略」サービスを提供しています。
350社以上のDX・データ活用プロジェクトを支援する中で、課題の本質を見抜き、投資対効果が見える形で施策を設計・実行してきました。15年以上にわたりアドテク・マーケティング領域で培った大規模データ処理や高可用性システム構築の技術力を強みとしています。
営業・CRM、カスタマーサポート、マーケティング支援、社内ナレッジ共有など、幅広い業務プロセスでのAI活用を企画から定着まで伴走し「PoCで止まらない」「コストと成果のバランスを取りながら全社展開する」ための実践的な支援を行い、持続的な成果を創出を支えます。
本格的なご相談の前にまずは軽い壁打ちから、貴社の状況に合わせた最適な進め方を一緒に考えませんか。お気軽にご相談ください。